最近ネット上で見かけるこんな記事。
書きました!YouTubeがラウドネス規格を導入!J-ポップやボカロ曲にも影響が?音圧戦争その終わりの始まり – What a Wonderful World t.co/hMJJF9h4zN
— mirgliP@Hizuru (@mirgliPilgrim) 2015, 3月 18
「アンチ音圧」というのは以前から叫ばれていましたが、
具体的な動きが出てきたということですね。
上の記事でも書かれている通り、
音圧をあげるという行為は
「他の曲より聞こえを良くする」ためのものです。
※詳しい話は上の記事にわかりやすくまとめてあるので割愛w
例えば、音圧上げてる曲Aと、上げてない曲Bを並べて聞いたとき、
Aの方が何か迫力があってかっこ良く聞こえる、みたいな。
しかし、最近の僕の音楽の聞き方は、
i-tunesなりYOUTUBEなりで作ったプレイリストを
BGM的にランダムに鳴らすという感じ。
パソコンで音楽聞いている人は割りとこんな感じの人が多いんじゃないでしょうか?
こういう場合、いちいち音量のばらつきがあると心地良いBGMにはなりません。
そういう意味ではこの「ラウドネス規格」は大歓迎。
しかし、音楽を作っている側からすると一大事です(笑)
これ、法律が変わるみたいな感じで、
一斉にすべての音楽がこういう基準になればいいですが、
対応していないところ(音圧上げてに作った方がいい場合)もまだあるでしょう。
そもそも、最近の音楽事情は、
フォーマットの多様化で、いろいろと実際に試してみないと心配な僕にとっては一苦労です。
例えば、出来上がった曲をチェックしてみるときに、
昔ながらのラジカセで聞いてみたり、ipodで聞いてみたり、携帯のスピーカーで聞いてみたり。
再生機器だけならいいですが音源ソースだって様々です。
CD、mp3、YOUTUBEなどなど。
※最近ではミスチルが新しいアルバムをUSBメモリ入りのハイレゾ音源で発売という記事が話題になってましたね
と、ちょっと脱線しましたが、
ちょうど「音圧どうしようか」という曲の作業をしていたので
勉強がてら調べたことを、ゆる~く、薄~く記事にしてみました。
(というかただ引用のリンクを張っただけ)

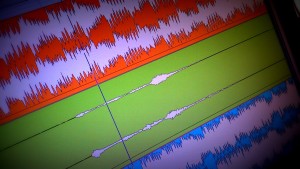


コメント